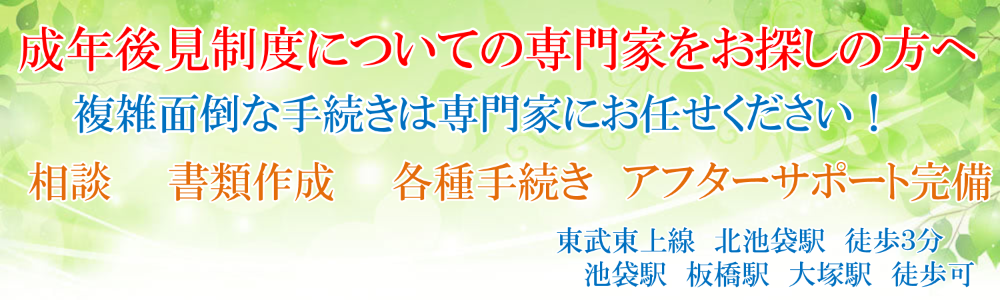成年後見制度について、こんな悩みはありませんか?

- どこで何の手続きすればいいの?
- 準備するものは?
- どの種類の後見」にすればいいの?
- 何度も役所に行く事になった。
- まずは相談したい。
成年後見の手続きは1人でやると大変です
必要書類を用意する事から始めますが、用意する書類は非常に多く大変です。
例えば
- 申立書
- 事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録
- 戸籍
- 住民票
- 収支報告書 など、ほかにも多くあります。
調べる事からはもちろん、専門知識が必要になるので非常に大変です。
成年後見は法定後見の補助・保佐・後見の3種類と任意後見があり、状況により医師からの診断書や提出する書類が違ってきます。
記入漏れや不備で受理されない事や、裁判所の決定で期待通りの結果が出ない事もあります。
成年後見制度の利用が始まると、財産管理をしっかりと行い、定期的に報告書を作成し裁判所に提出しなければなりません。
領収書のコピーや通帳のコピーなどを求められ、お金の流れに不明点があると裁判所から連絡が来る事があります。
成年後見制度は利用が始まってからのほうが大変です。様々な問題に臨機応変に対応しなければなりません。
ご依頼によるメリット、7つの特徴

無料相談ではケアマネジャーの資格を持った担当者が、ご本人の様子やお話からどの後見制度が適切なのか、どんな書類を準備すればいいかなどを分かりやすくご説明いたします。
あなたは当事務所へ申し込むだけで大丈夫です。
.jpg)
専門用語は使わず、分かりやすくご説明します。
不明点は遠慮せず、納得がいくまでお尋ねください。
.jpg)
成年後見制度は複雑な手続きです。ご自身で調べた方なら分かると思いますが、事前準備にかなり時間がかかります。
必要な事はこちらでお調べし、手続きに必要な法律、書類、記載方法など分かりやすくご説明をします。

お客様自身でご準備頂く書類についてはどのように収集するかを分かりやすくご説明します。
かかりつけ医や担当ケアマネジャーとも連携を取る事も可能です。

入金確認後すぐに業務開始となります。
後見の種類や準備により、どのくらいの時間がかかるのか、事前にご説明します。

ご自宅はもちろん、介護施設、病院、ご実家など出張での対応も出来ますので、お気軽にお問い合わせください。

定期報告やご本人様の様子など定期的にご連絡を差し上げます。
又、他の困りごとなどのご相談もいつでものりますし、必要な専門家など無料でご紹介しております。
ご相談からご依頼までの流れ
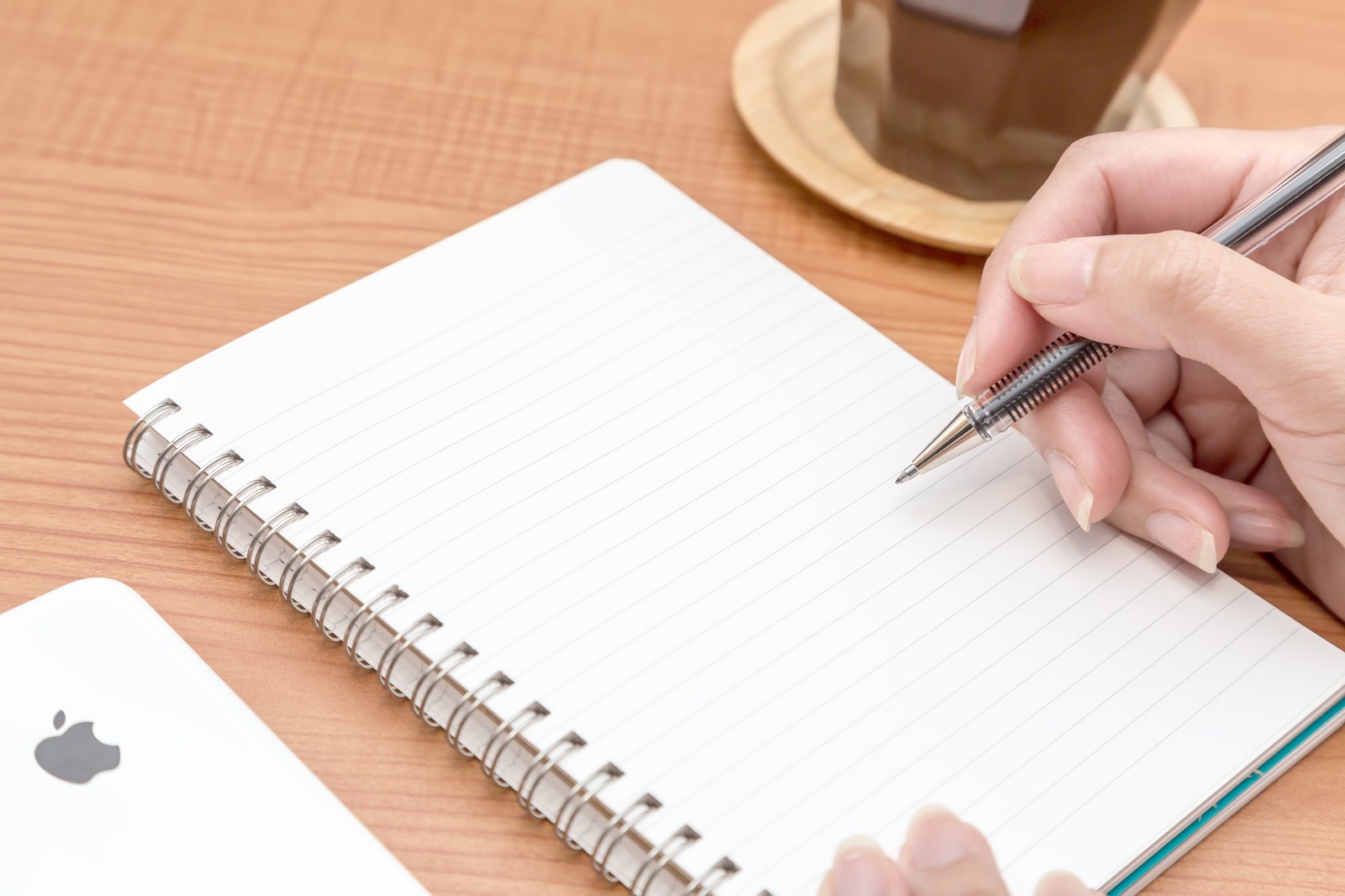
メールフォーム、又はお電話からお問い合わせください。
直接お会いして対応をご希望の方は、日程の調整を行います。
↓

詳しく状況を伺い、ご提案やご説明を行います。
今後の方針や費用についてご納得頂けたら、正式にご契約となります。
↓

必要書類や関係機関との打ち合わせなど、業務を速やかに開始し、定期的に進捗状況をご報告致します。
業務内容によっては、お客様にご用意頂く書類などがある場合がございます。
↓

業務完成。必要書類の受け渡し、残金がある場合は清算などを行います。
同時にアフターサポート、継続業務の開始。
メールフォーム
※メールフォームが使えない場合は info@imaura.com まで直接お問い合わせください。
よくあるご質問
原則としてメールや電話では無料で行っています。ご質問が多岐に渡り、専門的にご質問される、繰り返しご質問される場合には相談料を頂く場合がございます。
料金を頂く場合は事前にお伝えしますので、ご安心ください。
誰が誰に成年後見制度を利用するのか。親族との関係性や不明な事が分かる書類などをお持ち頂くと、こちらもお答えしやすいです。
報酬表を記載しています。こちらをご参考ください。また、ご契約の際にもしっかりとご説明し、それ以上費用が発生する事はありません。
記載のない報酬額に関しても事前にしっかりとご説明やご提案をさせて頂きますのでご安心ください。
はい可能です。ご指定頂ければ、喫茶店などでもお会いしています。
成年後見制度とは

人は皆、高齢や障害により記憶力が衰えていきます。
最近では認知症という言葉もテレビで頻繁に聞くようになりました。
仕事をして、買い物をして、ご飯を作って、遊びに行ってと、私たちは日常を何気なく過ごしていますが、その当たり前に出来ていた事が出来なくなってしまったとしたら・・・
あきらめますか?
そんな事は無いはずです。何かをしたい気持は失われるものではありません!
少しの助けがあれば今までと変わらない生活が送れる事はたくさんあります。
車があれば遠くへ行く事が出来ます。
足を骨折した時に杖があれば歩く事が出来ます。
通訳がいれば外国人と話せます。
私たちは日々の暮らしの中で様々な助けを必要とし、助けられています。
後見制度とは少しの手助けで、今までと同じような暮らしが送っていくのを支援する制度です。
介護保険制度と同じ時期に発足され、徐々にではありますが、知名度、実績が上がってきています。
後見の種類
法定後見と任意後見の2つがあります。法定後見はさらに本人の状態により3種類に分かれます。
次に細かくどのようなものか簡単に説明致します。
法定後見
申立て等により家庭裁判所により後見人が選任され、本人の身の回りの手続きなどに関して助けてくれる制度です。
本人の状態により次の3つに分かれます。
後見
一人では日常生活を送る事が困難で誰かの支援がいつも必要な状態。
重度の認知症と診断された方。
重度の障害をお持ちの方。
徘徊、精神状態不安定な方。
身寄りがいない方。 など
介護度の目安として介護3〜5程度
(介護認定を受けていなくても後見人がつく場合があります)
保佐
日常の買い物はできるが、借財や財産処分など重要な事が心配で、その時だけは支援が必要な状態。
軽い認知症で重要な説明などが理解できない時がある方。
時々物忘れがあり、誰かに迷惑をかけることがある方。
契約などで付き添いが必要な方。 など
介護度の目安として要介護1〜3程度
(介護認定を受けていなくても補佐人がつく場合があります)
補助
日常の買物、財産管理などは1人で出来ているが、不安があり誰かにやってもらったほうが本人の為になる状態。
物忘れが時々ある方。
訪問販売が断れない方。 など
介護度の目安として要支援、要介護1程度
(介護認定を受けていなくても補助人がつく場合があります)
任意後見
判断能力がおとろえる前に、将来の不測の事態に備えて財産管理、療養看護等について、自分の信頼できるものに支援を頼む契約です。
法定後見と違い、委任契約なので、自分で自分の事をある程度決める事が出来ます。
公正証書で委任契約を結び、自分が元気な状態の時は今まで通りの生活を送り、不測の事態になった時に初めて契約の効力が発生します。
具体例
両親が高齢になり悪徳商法から守りたい。
障害を持つ子供が残された時の世話を頼みたい。
身寄りがなく介護支援が必要な時が来た場合。
自分の財産を信用できる第三者に管理してもらいたい。
判断能力が少し衰えてきたと感じた時。
残していく家族を守りたい。
など、簡単に例をあげてみました。もっと詳しく知りたい方は「法務省 成年後見制度」に分りやすくQ&Aでまとめてありますので一度目を通されると良いかもしれません。
どれくらいの費用がかかるのか
法定後見の場合
- 申立収入印紙 800円〜1,600円(成年後見は800円)
- 登記印紙 4,000円程
- 郵券 5,000円程(家庭裁判所によって異なる)
- 鑑定料 60,000円〜150,000円程 (判断能力の判断)
上記の法定費用がかかります。
鑑定は行わない事もあり、それぞれの状態によります。
また、法定後見の場合、報酬は家庭裁判所により決められますので、法外な値段を要求される心配はありません。
任意後見の場合
お互いの話し合いにより契約が交わされることになります。
どのような内容で契約を交わすかにより話し合いで金額が決まります。
契約内容は公正証書で残すので、その費用も負担しなければなりません。