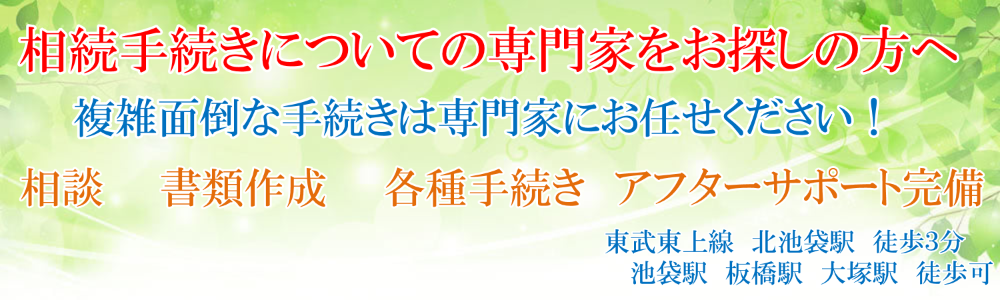相続人の範囲について

法定相続の場合における優先順位は以下のようになります。
- 配偶者と子供の場合 配偶者1/2 子供1/2
- 配偶者と両親の場合 配偶者2/3 両親1/3
- 配偶者と兄弟の場合 配偶者3/4 兄弟1/4
配偶者は常に相続人になります。
実際の例をみてみましょう。
1の場合において、妻と子供2人(A、B)が相続人とし、300万の財産があるとします。
妻と子供で各150万分で分ける事になります。更に子供の150万はA75万、B75万で分ける事になります。
2の場合において、子供がおらず両親が健在、300万の財産があるとします。
妻は200万、両親は100万で分ける事になります。両親が2人とも健在なら、100万を2人で分け両親は50万ずつになります。
3の場合において、子供も両親もおらず、兄弟姉妹が1人健在、300万の財産があるとします。
妻は225万、兄弟は75万で分ける事になります。
ではそれ以外の場合はどうなるのでしょう?
子供はいないが、孫がいる。
孫は相続できます。この場合、本来は子供が相続できる権利を孫が代わりに相続する事になります。
これを代襲相続といいます。更に子供も孫もいないが、ひ孫がいる場合も同じく相続できます。玄孫の場合も同じです。
兄弟姉妹の場合、甥や姪の両親がいない場合に相続権利を相続します。但し、その先、甥や姪の子供にはこの権利は発生しません。
別れた配偶者との間に子供がいる。
子供は相続できます。自分の子供ですから当然の権利です。
少し前までは婚姻関係ではない場合、分配に差がありましたが、現在は改正され平等に扱われます。
音信不通の親族がいる。
このような場合、相続人の調査を行い、現在の状況を確認する必要があります。
このほかにも人それぞれの状況により、わからない事は多いと思います。
相続が起きた時は法律に沿って正しい手続きが必要になります。
必ず相続人の調査を行い、残された人同士でトラブルにならないことが一番大切です。